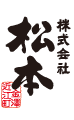私と社長とでJAはくいへ、新たな商品を求めて
私と社長とでJAはくいへ、新たな商品を求めて農家プロジェクトは、石川県内の農家と当社が深くつながり、そして農家と当社のお客様をつなごうというものです。
こんにちは。「未来を見つめる農家プロジェクト」の推進役を任されている、インターン生・金沢学院大学3年の谷口稀保(たにぐち きほ)です。
~ 農家プロジェクト:捨てられていたものに命を吹き込む~
シリーズの 11回目は、石川県羽咋市宝達志水町のJAはくいさんです。
6月1日 JAはくい南部育苗センターを訪れました。
と、いうのは。
果樹を育てる時に摘果という作業が行われます。
ネットで調べると、付けた実が多すぎたり、一か所に固まったりした時の間引き作業と記載されています。木の本体が疲れないように、かつ一個一個の果実にたっぷりの栄養分をいきわたらせて美味しく、かつ大きな実を実らせたり、枝を保護するために、余分な果実をつみ取ることだそうです。
摘果した実は棄てられてしまうだけで、もったいない気もしますが摘果は大きな美味しい果実のためには必要な作業なんです。その中でも一部は商品として売られているものもあります。有名なのはスイカやメロンやりんごで摘果したメロンの漬物は田舎のおばあちゃんがよく食べていたそうです。
■ 新しい需要を生むことが重要です
社長によるとここ10年で本来は棄てられていたはずの摘果した桃の甘露煮が「若桃」という名で爆発的に売り上げを伸ばしているそうです。一般的にはまだ名前は知られていませんが、㈱松本の販売経路の業務用食品の分野ではおせち料理としては定番となっているそうです。

若桃の瓶
原料の調達は、岡山・和歌山・愛媛県がメインで大手の農家から直接やJAを通して摘果した実が集められ甘露煮に加工されています。結果としてゼロから新しい需要を生み出したのです。
社長はこれを「ベンチマーク」して新しい需要を生み出そうと模索しているのです。でも私的には難しいカタカナは使わないで「他人の良いところを真似する」でいいと思うのですよ。
前置きが長くなりました。以上の考察があって、今回は若桃に代わる、青い実を探して私と社長が二人で羽咋へ向かったのです!
■ イチジクの代わりにスモモを提案
もともとイナト(石川県農業振興機構)に対してイチジクの摘果した実を加工に使いたいと相談したところ、石川県の一大産地である宝達志水町のJAはくい の営農部の高嶋さんを紹介されたのです。
まず高嶋さんとのアポ取りの電話での話では「宝達志水町のイチジクの栽培では摘果はしないのです。」と最初にとどめを刺されたそうです。でも高嶋さんは、「それならスモモは、摘果するけどどうかネ」と提案してくれたのです。
すももは、その実が木にゴロンゴロンとまとまってできるそうなのですが、こぶし一個分くらいの間隔をあけながら、摘果していくそうです。
そしていまここJA羽咋・押水で二人と私は出会っているのです。

松本社長と高嶋さんとの打ち合わせ
■ 高嶋さんとの打合せ内容
高嶋さんは、摘果した実に対して、
「摘果した実は、なんとも青臭くて、えぐみと渋みがたくさんだよ」とおっしゃっていました。
「こんなの商品にできるのかね?」
と最初は疑われておりました。
ということで!
以前から会社にある、若桃のシロップ漬け、試食していただきました。

若桃を確認する高嶋さん
*桃の摘果の実とは、
桃を栽培する時に重要となるのは摘果(てきか、てっか)作業です。文字通り、あえて実を摘むという作業のことです。そのほとんどが落とされ廃棄処分にしてしまいます。
これを甘露煮にしておせち材料にしたのが始まりでした。今では多くのおせちに使われ、その青い色が食欲を深めてくれています。また「いつまでも若々しくいられますように」という意味を込めてに詰めているのです。
「こんなに甘いの?」
「え、甘くなるの?」
「おいしい!」
「これはおいしいワ」と、絶賛しておりました。
しかもその時持って行った、若桃の試食用が、少し凍らせてあって、
「アイスみたいでおいしい」と言ってましたね~
そして、そして、うまいと言いながら、もう一個、パクっと食べてくださいました。
こういう反応は、なんだかとってもうれしく、ワクワクしてしまいます。
「摘果の実がこんなんになるんなら、ちょっと、部会の人にも食べさせたいし、これ取っておこう!」と、すぐに冷蔵庫にしまっていました。
そして、すももの摘果した実を5月24日くらいに摘果した実を、一週間ほど冷蔵庫で、保存してくれていたものを見てくれました。

スモモのアップ
見た目は、若桃そっくりです。
シロップ漬けにするけれども、甘いだけじゃなくて、スモモの酸味の部分も少し出たら、これまでとは、また違ったものになるのではないかなと思います。

スモモをカットして種を確認
■ JAはくい の試み
高嶋さんは、これまでにいろいろと、作物を加工できないかと考えてきていたそうです。
おもしろいのはスイカの加工でした。スイカを半乾燥させてみると甘みが凝縮されて、キャンディのようになったそうです。これがとても美味しかったけれど、まったく売れなかったそうです。
あの大きなスイカを丸ごと輪切りにして乾燥させて作るそうですが、出来上がりを想像すると私の顔より大きいスイカキャンディーなんて、とても楽しくなります。
また、イチジクは昔から捨てるところがないといわれているそうです。
イチジクの実は、そのまま食べることができるし、
葉は、香りが強くお茶などにもできるそうです。
だからお茶を作ってみたそうです。
とてもいい香りだったけど、これもあまり売れなかったそうです。
私が一番驚いたのは、枝も使えるということです。
枝は、お風呂に入れると、とろみが出るらしいのです。
気持ちよさそうですね~。
JAにいると色々なものが作れるみたいで、私は一生の仕事としてちょっと気がそそられました。(社長、すみません。気にしないでください。)
昔からあるということで…。チョットうんちくを。
イチジクの歴史がいつからあるか知っていますか?
いろいろと諸説は、あるんですけれど、イチジクは、あの有名なアダムとイブのお話にも出てくるらしいのです。アダムとイブっていつの話?気になったので調べました。
創世記の話なので、6000年前らしいです。
もう想像つかないですよね…。
そんな昔からある歴史あるフルーツなんですよネ。
■ 試作品が完成しました
6月8日
少し期間は空きましたが、なんとシロップ漬けの試作ができました。
私も試食をしてみました。

すももの摘果で試作一号
おいしい。
色は加熱の為に悪くなってしまっているけれど、おいしいです。
でも少し色の悪いのを気にして社長に聞くと、銅鍋で炊けば色は出るし、温度調節次第で解決する問題と言われて、ホッとしました。
本当に青くなるのでしょうか…?(社長は自信たっぷりでしたが…)
でも種が、最初に摘果した実を切った時より、全然大きく存在感がありすぎています。
なんとはじめて高嶋さんから見せられた時よりも、炊くことにより大きく硬く感じるるのです。
それを私と社長とで若桃の製造メーカーの工場長にも内緒で話を聞くなど、あれやこれやと調べていると対策が分かりました!
これでまた一歩、前に進みました。
来年の摘果した実を使って、完成形に近づくのが楽しみです。
今回は社長が、ほとんどメインでした…。悔しい(笑)
これから、イチジクの出荷が始まります。
宝達志水町のイチジクとスモモ、皆さん買いましょうね。
株式会社 松本
https://matumoto.co.jp/
株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。
この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。
当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。
■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです
料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。
株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。
私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。
「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。
気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。
※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。
■「金沢を世界一の美食のまちに」
私たちが目指すのは、ただの商いではありません。
食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。
スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。
この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。
一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?
■ お取引先の一例
嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、
地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。
たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――
“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。
代表取締役 松本信之
農林水産省認定 6次産業化プランナー
フードアナリスト NO.25042013
【連絡を検討中の企業様へ】
★TEL:076-232-2355
こちらからお電話ください。
(株)松本の代表番号になります。
電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。
【電話対応時間】平日9:00~16:30
下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。
問い合わせフォームは24時間対応しています。
些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!
メールアドレスからでもどうぞ!
oishi@matumoto.co.jp