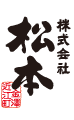この青い色と香りが魅力です
ふっくらとした茎をかみしめた時のあの奥山の香り、独特の柔らかさが青干し、緑干しぜんまいの身上です。日本の食文化は豊かで多様、そして奥が深い。その数ある食材の中でも特に注目されているのが青干し、緑干しぜんまいです。
プロローグ
見た目はシンプルながら、この食材は日本の料理に独特の風味と風格をもたらします。今回は、青干し、緑干しぜんまいの歴史、特徴、そしてプロの調理師がどのようにこれを活用しているかに焦点を当てています。
青干しぜんまいと緑干しぜんまい
地域によっては混同され同じに扱われますが、正確に言うと違うものです。その違いは、主に加工方法に起因します。

採り子さんによってゼンマイが集められます。この採り子さんが少なくなってきました。
特定の地域では、青ゼンマイを特に上質として扱い、別の地域では緑ゼンマイを好むことがあるため、その地域特有の加工方法や呼び方が存在するのです。また、産地や市場、業者によっても、青ゼンマイと緑ゼンマイの定義や呼び方が異なることがあるため、購入や使用時には、その特性や風味をしっかりと確認し、具体的な使用目的や好みに合わせて選ぶことが大切です。
加工方法の違い
青干しゼンマイ:青ゼンマイの特徴的な青みがかった色は、特定の加工方法によって得られます。具体的には、ゼンマイを締め切った山小屋の中などで松葉や木の葉を燻して乾燥させることで、この色が強調されることが多いです。この燻製のような加工方法により、青ゼンマイは独特の香ばしい風味を持ちます。
この名称は、ゼンマイが持つ独特の青みがかった色を指すことが多く、燻し乾燥させることで、この色が強調されます。

ゼンマイを干している様子
緑干しゼンマイ:緑ゼンマイは、天日干しや自然乾燥の方法で乾燥させたゼンマイでゼンマイが持つ自然な緑色を指しています。特別な燻製のような加工をせず、ゼンマイ本来の色を保っています。この方法では、ゼンマイの自然な風味が強調され、天日干しや自然乾燥の方法で乾燥させたゼンマイがこの色を持つことが多く、自然な風味が楽しめ、ゼンマイ本来の味を感じることができます。
一般的には、青ゼンマイの方が特有の風味があり、その風味を好む人にとっては上等とされることが多いです。しかし、緑ゼンマイは自然な風味が強く、これを好む人も多いため、どちらが上等であるかは好みの問題とも言えます。
背景 (Background)
青干し、緑干しぜんまいは、日本の伝統的な食材であり、春の訪れを告げる食材として知られています。その風味は独特で、料理に深みと味わいを加えることで知られています。
春先に収穫されたぜんまいを天日で干して乾燥させ、冬季の保存食として重宝されていました。ぜんまいは冬の寒さの中、雪の下ではぐくまれ、雪が解けるとアクが適度に抜け、摘み取るくらいの大きさに育つとえぐみが少なくなり美味しくなります。
また青干しゼンマイとは、戻すと緑色になる干しゼンマイのことで、木の皮で屋根を葺いて小屋がけして、石を組んだ4ⅿ四方もある竈(かまど)に、一日中松葉を燃やしてぜんまいを蒸しって燻製にしたものです。
この松葉での燻製方法により、青干しぜんまいはさらに独特の風味と香りを持つことになり、料理に深みと特別感を与えます。
この青干し、緑干しぜんまいの歴史は古く、日本の古くからの食文化を反映し、日本の食の多様性と季節の変化を祝う文化の美しさを示しています。これらの情報がプロの調理師やシェフの皆様にとって、新しいインスピレーションや知識を提供する助けとなることを願っています。
目的 (Purpose)
水になったゼンマイは日本中どこへ行っても見ることはできますが、プロの調理師やシェフにとって、青干しぜんまいは、その特別な風味と食感で、家庭やほかの店との違いを引き立てる食材です。料亭や高級レストランでは、この食材が持つ独特の風味を活かし、独創的でエレガントな料理を提供することで、お客様に特別感を提供しましょう。
戻し方 (Preparation)
干しぜんまいを調理する前には、まず戻す作業が必要です。これは非常に簡単で、以下の手順で行います。

まずはぬるま湯から戻し始めます。
① ぜんまいを約40℃(冬は約70℃)のお湯に約2時間つけます。
お湯はたっぷりと。また、お湯が熱すぎるとぜんまいが裂けてしまうので注意。
② 5~6 回ほどお湯を変えてアクを抜き、そのたびにぜんまいを洗います。
ぜんまいが傷つかないように、やさしく洗うのがコツ。
時間が経つにつれて、平べったかったぜんまいが、丸く元に戻ってきます。

銅鍋を使うと色よく仕上がります。
③ ぜんまいを洗い終えたら、先ほどより少しぬるめのお湯を入れ蓋をします。夏なら1日半おきます。
④ まだ完全には戻り切っていないので端の方を10本程度まとめて形を整え少量の晒し水の中で皴がなくなるまで最終的に戻します。ゼンマイが均一に戻り、調理時の食感が向上します。
⑤ このまとめてあるゼンマイごと味を含ませ、大原木(おはらぎ)状態にして盛り付けます。
結果 (Results)
干しぜんまいを利用した料理は、料理のプロフェッショナルによって高く評価されています。
その独特な風味と食感は、日本料理だけでなく、洋食や中華料理においても新しい風味を発見することを可能にします。プロの調理師ご用達の食材として、青干しぜんまいは多くの料理人に愛され、その可能性を探求され続けています。
エピローグ
干しぜんまいは、プロの調理師やシェフにとって、日本の美味を表現するための貴重な食材です。
その独特の風味と食感を活かし、新しい料理の創造に挑戦することで、日本の食文化の豊かさを再認識し、料理の世界に新たな可能性をもたらします。
しかしこの貴重な食材も採る人の高齢化と手間の多さのために年々作る人が少なくなり、もはや貴重品となってしまいました。あと5年も立たないうちに消えていく運命となっています。

あとは端を揃えて最後の仕上げにかかります。
さあ、いまのうちに手に入れた青干しぜんまいを調理師して、その魅力を自らの目と舌で確かめてみてください。
★ 参考:家庭で使う赤ゼンマイとは
一般的に家庭でよく使われる干しゼンマイで、その赤茶色の色合いが特徴的です。この色は、ゼンマイを茹でる際に酸化が進行し、変色することによって生じます。
独特の風味と食感があり、酸化による微かな酸っぱさが料理のアクセントとして利用されることもあります。
赤ゼンマイは、煮物や和え物、おひたし、サラダなど、さまざまな料理に利用されます。特に、醤油や砂糖、みりんをベースにした煮汁で煮込むと、赤ゼンマイの旨味が引き立ちます。
日本の伝統的な食材として、多くの家庭や料亭で愛されてきました。その独特の風味や食感は、日本の四季を感じさせてくれるものです。ぜひ、この伝統的な食材を活かした料理を楽しんでみてください。
株式会社 松本
https://matumoto.co.jp/
株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。
この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。
当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。
■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです
料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。
株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。
私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。
「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。
気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。
※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。
■「金沢を世界一の美食のまちに」
私たちが目指すのは、ただの商いではありません。
食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。
スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。
この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。
一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?
■ お取引先の一例
嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、
地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。
たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――
“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。
代表取締役 松本信之
農林水産省認定 6次産業化プランナー
フードアナリスト NO.25042013
【連絡を検討中の企業様へ】
★TEL:076-232-2355
こちらからお電話ください。
(株)松本の代表番号になります。
電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。
【電話対応時間】平日9:00~16:30
下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。
問い合わせフォームは24時間対応しています。
些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!
メールアドレスからでもどうぞ!
oishi@matumoto.co.jp