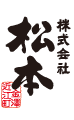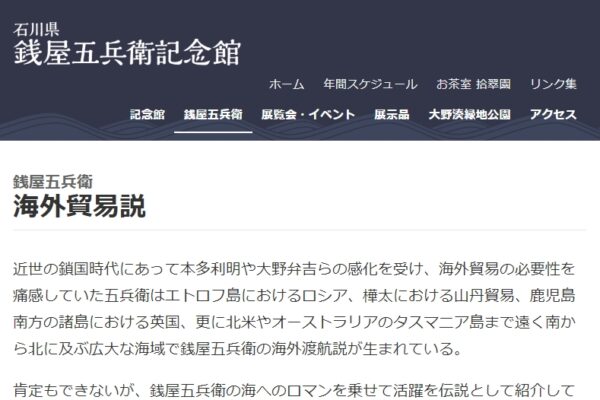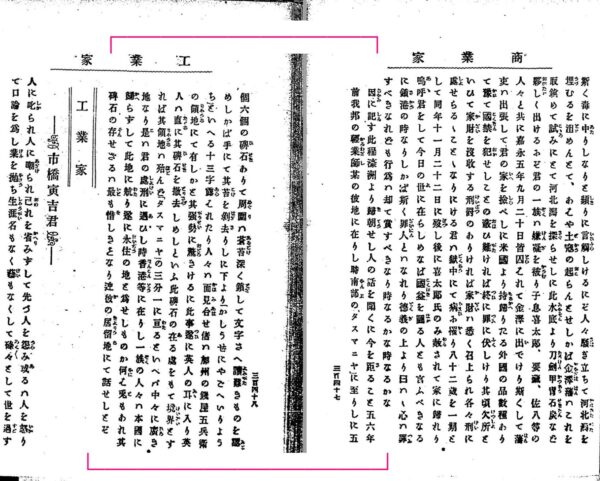佐渡国小木民俗博物館から、実物大の千石船が展示されています
みなさん、かぶら寿しをご存じですか?北陸を代表する冬の味覚で、特に金沢では昔から愛されています。その歴史を探ってみると、なんと銭屋五兵衛という歴史的な人物に行き着く話があるんです!
かぶら寿しの始まり
食材の旅「かぶら寿し」の項でもレポートしましたが、江戸時代にはかぶら寿しで使う「鰤」は武家社会のもので庶民には贅沢品として食べるのを激しく禁止されていました。
そんな中、時代が江戸後期に移ると、武家の食文化が町民にも広がるようになり、かぶら寿しが町民文化として定着していったとされています。そのきっかけの一つが、豪商・銭屋五兵衛の存在だったのです。
銭屋五兵衛とかぶら寿しの密かな楽しみ方
銭屋五兵衛は、江戸時代後期の金沢に実在した豪商で、千石積みの持ち船を20艘以上、全所有船舶200艘を所有し、全国に34店舗の支店を構え全資産は300万両といわれていました。しかし、いくら富を築いても鰤を堂々と食べることはできなかったのです。

「石川県銭屋五兵衛記念館」にて、五兵衛の肖像画
そこで五兵衛は、寒鰤を薄切りにして青かぶらに挟み、あたかもただの野菜の漬物のように見せかけて密かに楽しんでいたという逸話が残されています。これが町民文化への広がりの一因になったかもしれないと考えると、なんともユニークですよね!
贅沢の価値を見直す
現代では、お金があれば世界中の美味しいものが手に入ります。でも、当時の人々が味わっていた「贅沢のスリル」や「工夫の味わい」には、今とは違った特別な価値があったのではないでしょうか。
冬の金沢を訪れた際には、ぜひかぶら寿しを味わってみてください。そして、一口食べるごとに、武家文化や銭屋五兵衛の知恵、そして当時の人々の工夫に思いを馳せてみてはいかがでしょう?
禁制を破る大胆な密貿易・交易範囲がすごすぎる!
江戸時代、日本は厳しい鎖国政策の真っただ中でしたが、そんな時代の制約に屈しなかったのが銭屋五兵衛です。「抜け荷」と呼ばれる密貿易を展開し、その規模がなんと壮大!
北は北海道の礼文島や樺太でアイヌやロシア人と交易し、南は薩摩藩を通じて奄美大島と沖縄の間にある口永良部島でイギリス人とも取引を行っていたとされています。

礼文島にある銭屋五兵衛貿易の地の碑
さらに驚くべきは、五兵衛の船がジャワ島やオーストラリアのタスマニア島、そしてアメリカのサンフランシスコにまで到達していたという噂。あくまでも噂ですがタスマニアの話は信憑性があり、蒸気機関もない日本で江戸時代とは思えないスケールの大きさに圧倒されますよね!
歴史が語る五兵衛の足跡
五兵衛の壮大な密貿易については、いくつかの資料や証言が残されています。たとえば、深井甚三 著(富山大学教授)『銭屋五兵衛と抜荷』では、次のようなエピソードが紹介されています。
・竹島(鬱陵島)でアメリカの捕鯨船と交易を行っていた。
・樺太では、山丹人に家具を売り、特産品を仕入れて大阪で売却。
・ロシア沿海州の港に米を運び、年間2万石もの量を売却。
さらに、ロシアのプチャーチン使節団の記録や、勝海舟の「幕府も五兵衛の密貿易を黙認していた」という証言もあり、当時の五兵衛の活動がどれほど特異だったかがわかります。
タスマニアで発見された謎の石碑
読売新聞の記事になり一躍有名になったタスマニア島で発見された「加州銭屋五兵衛領地(かしうぜにやごへいりようち)」と刻まれた石碑も注目に値します。この石碑は、五兵衛がタスマニアを交易拠点として利用していた可能性を示唆しています。(残念ながら、イギリスの陶器会社によって持ち運ばれたといいます)

タスマニアにあった五兵衛の碑のイメージ
当時タスマニアの農園主が農産物不況により土地を島外の者へ売却していたという記録やタスマニアの古文書館や州立図書館の資料に記録が残されていて、当時の現地新聞に、この石碑を見たとする日本人芸人の記録があります。
この時代に日本の商人がタスマニアで活動していたかもしれないという事実は、まさに驚きです。
19世紀初頭のタスマニアはクジラ漁や羊毛産業が発展していた時期であり、五兵衛がこれらの産業とどう関わっていたのか、興味が尽きません。もしこの石碑の由来が解明されれば、日本とタスマニアの歴史に新たな1ページが加わるでしょう。
銭屋五兵衛が教えてくれる冒険心
「加州銭屋五兵衛領地」と刻まれた石碑は、五兵衛の挑戦心と行動力を象徴するものです。
厳しい時代背景の中で、未知の領域に果敢に挑戦したその姿勢は、現代を生きる私たちにも大きなインスピレーションを与えてくれます。
江戸時代のイノベーター(革新者)
銭屋五兵衛が世界に飛躍していたという説は、密貿易などで加賀藩自体が幕府の処置を受ける可能性があり五兵衛の口封じとともに具体的な取引記録は消され、口永良部島にあった英国人が居住する西洋館も、薩摩藩が直ちに西洋館を破壊し、密貿易の証拠を隠滅しました。
そのため直接の取引を示す史料による裏付けが難しい状態にありますが、五兵衛の家から多数の舶来品が発見されており、これが密貿易の証拠としてわずかに残されています。
銭屋五兵衛は、日本の物流を新たな次元に引き上げた革新者でした。
その冒険譚がどこまで真実であるかはさておき、彼の物語には想像を超えるスケールが広がっています。「江戸の海のイノベーター」とも言える五兵衛の足跡をもっと知りたくなります。
私達も郷土の先達として彼を見習いフードビジネスにイノベーションを起こしていきたいと考えています。
ただ処刑されるのは困りますが・・・・。
株式会社 松本
https://matumoto.co.jp/
株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。
この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。
当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。
■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです
料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。
株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。
私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。
「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。
気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。
※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。
■「金沢を世界一の美食のまちに」
私たちが目指すのは、ただの商いではありません。
食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。
スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。
この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。
一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?
■ お取引先の一例
嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、
地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。
たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――
“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。
代表取締役 松本信之
農林水産省認定 6次産業化プランナー
フードアナリスト NO.25042013
【連絡を検討中の企業様へ】
★TEL:076-232-2355
こちらからお電話ください。
(株)松本の代表番号になります。
電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。
【電話対応時間】平日9:00~16:30
下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。
問い合わせフォームは24時間対応しています。
些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!
メールアドレスからでもどうぞ!
oishi@matumoto.co.jp