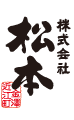炭火での鰻の焼き工程。焼きは一生とも言われる
2024年7月、横浜市の京急百貨店内の飲食店で販売された弁当により、集団食中毒が発生しました。これを受け、保健所は手洗い方法の見直しや従業員の健康確認と記録の徹底を指導し、改善されたため9月11日には営業禁止処分を解除しました。
この事件では、7月24日と25日に販売された1,761個の「うなぎ蒲焼」と「うなぎ弁当」を食べた159人が嘔吐や下痢などの症状を訴え、90代の女性が死亡しています。原因は、従業員の手洗い不足と手袋の未使用であるとされ、『黄色ブドウ球菌』が検出されました。さらに、ふき取り検査では調理場の作業台からも同じ菌が検出されました。
従業員の衛生管理が徹底されていなく、従業員の体調や手や指の傷などの健康状態に関する記録表も十分に記載されず、責任者による確認も行われていなかったことが明らかになっています。
※ 黄色ブドウ球菌は、人の手指・鼻・のど・耳・皮ふなどに広く生息し、健康な人の40%が保菌しています。だからこそ気をつけなければいけないのです。
営業停止の解除は行われたものの、「従業員への十分な衛生教育が行われていなかった」、「生産能力を超えた調理が行われたことが食中毒の危険を増大させた可能性がある」との報告がされています。
食品業界に携わるプロとして、このような事例は決して他人事ではなく、自らの現場においても常に見直しと改善を求められる教訓であると言えるでしょう。
手袋は万能ではありません
「手袋をしていれば安全」という誤った認識が多くの現場で蔓延しています。しかし、手袋を着けたまま鼻を擦ったり、金銭を扱ったり、ドアノブや段ボールを触ったりすることで、かえって感染を拡大させることがあります。
手袋の使用はあくまで補助的なものであり、その効果は適切な使用と徹底した衛生管理が伴わなければなりません。

手袋をつけて作業するのが原則
手袋を使用する際の基本的なルールとして、作業ごとに手袋を交換することが求められます。同じ作業を続けている場合でも、定期的に「衛生タイム」を設けて手袋の交換を行い、白衣に付着した毛髪やホコリを粘着ローラー(通称・コロコロ)で除去することが大切です。
さらに、手袋を着けているからといって、手洗いを怠るべきではありません。手袋の下に手指の菌が残っていれば、そのまま感染源となる恐れがあります。
プロとしての責任感を持ち、常に衛生管理を徹底することが重要です。
なぜ食中毒が発生したのか
通常、うなぎの蒲焼で食中毒が発生することは珍しいことです。特に店内で調理され、すぐに提供されるものであれば、リスクは低いはずです。しかし、土用の丑の日に向けた需要の高まりに対応するため、大量の仕込みが行われたことが今回の事態を引き起こした要因の一つではないかと考えられます。

うなぎ蒲焼き
あくまでも想像ですが、地下一階の販売所、10Fの店舗、百貨店内のイベント用の厨房だけで本当に当日の調理が出来たのでしょうか。前もって大量に仕込んだうなぎを、粗熱を取らずに冷蔵庫に保管してしまったことで、冷蔵庫内で蒸れ、菌が増殖した可能性はないのでしょうか。
通常、その日にさばいて、焼き上げたうなぎは、その日のうちに提供されるべきですが、このようなプロセスが崩れると、危険な状態を招くことがあります。これは、過去から学びながら適切な工程を守ることの重要性を強調する事例です。
過去の事例と共通する問題点
国立保健医療科学院(厚生労働省所管の国立研究機関であり、政府機関の一部)のデータを振り返ると、2018年7月25日に愛媛県今治市で発生した大規模食中毒事件もまた、うなぎ料理に関連していました。

国立保健医療科学院のHPより
この事件では、384名のうち299名がサルモネラ菌による下痢、腹痛、発熱などの症状を訴えました。この事例においても、夏場の高温環境における温度管理や衛生管理の不徹底が原因となっています。
この事件では、うなぎを調理した後、白焼き状態でトロ箱に入れ、常温で保管していたことが問題となりました。
さらに、調理従事者は加熱前後に手袋を交換せず、手洗いを怠っていたこと、調理の手順書が存在せず、経験則に頼っていたことがリスクを高めました。
こうした事例は、過去の失敗から学ぶことの重要性を教えてくれます。
昨年の駅弁大会からの教訓
昨年、京王百貨店で開催された駅弁大会においても、1日あたり18,000個もの駅弁が販売され、そのうち521人が食中毒の被害に遭いました。
原因は、米飯を外部業者から納品する際の温度管理に問題があり、米飯がまだ熱い状態で副菜を乗せてしまったことでした。このような温度管理のミスが食中毒の主な要因となったのです。

デパートでの大駅弁大会のイメージ
この事例も、京急百貨店でのうなぎ事件と共通する問題点を抱えています。
温度管理の不備: 京王百貨店の駅弁事件でも、米飯の温度管理が不適切であったことが原因です。同様に、京急百貨店でのうなぎや弁当の温度管理も不十分であった可能性があります。特に夏場は、適切な温度管理が欠かせません。
衛生管理の不徹底: 両事例とも、手洗いや手袋の使用、従業員の衛生管理が徹底されていなかったことが共通しています。
記録管理の不備: 従業員の健康状態や衛生管理に関する記録が不十分であったことも、両事件に共通する問題です。
二次汚染のリスク: 調理器具や作業環境を通じた二次汚染が、両事例で発生している可能性があります。
大量調理のリスク: 繁忙期の大量調理は、通常以上に厳密な衛生管理を必要とします。大量生産に伴うリスクを軽視してはなりません。
危険温度帯の管理: 食材が10度から60度の範囲に長時間留まると、菌が急激に増殖します。両事例とも、危険温度帯の管理が不十分だった可能性があります。
これらの要素を踏まえると、京急百貨店の事例もまた、手洗い不足だけではなく、温度管理や衛生管理の不徹底が複合的に影響した結果であることが見えてきます。
過去から学び未来を築く
私たちは歴史を学ぶことで、過去の教訓を未来に活かす力を養います。過去の事例を他人事とせず、自らの現場に活かすことが、プロの調理師やシェフとしての責務です。同じ過ちを繰り返さないためにも、細心の注意を払いながら、衛生管理や調理プロセスの改善に取り組むことが求められます。
「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」というビスマルク(旧ドイツ・プロイセンの宰相「鉄血宰相」と呼ばれた)の言葉が示すように、過去の失敗や成功から学び、それを日々の業務に反映することが、真のプロフェッショナルである証です。食材のプロとして、時間的にも空間的にも広い視野を持ち、過去の教訓を活かして未来を築く力を身につけていきましょう。
あなたの現場でも、過去の事例を他山の石として、常に見直しと改善を行いましょう。それが、プロフェッショナルの誇りであり、特別感のある料理を提供するための第一歩と考えるものです。

過去と未来のイメージ
株式会社 松本
https://matumoto.co.jp/
株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。
この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。
当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。
■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです
料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。
株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。
私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。
「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。
気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。
※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。
■「金沢を世界一の美食のまちに」
私たちが目指すのは、ただの商いではありません。
食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。
スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。
この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。
一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?
■ お取引先の一例
嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、
地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。
たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――
“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。
代表取締役 松本信之
農林水産省認定 6次産業化プランナー
フードアナリスト NO.25042013
【連絡を検討中の企業様へ】
★TEL:076-232-2355
こちらからお電話ください。
(株)松本の代表番号になります。
電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。
【電話対応時間】平日9:00~16:30
下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。
問い合わせフォームは24時間対応しています。
些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!
メールアドレスからでもどうぞ!
oishi@matumoto.co.jp