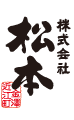かって駅弁は列車に乗って食べるものでしたが・・・
駅弁の起源は、ゴマをまぶしたにぎりめし2個とタクワン2切れを竹の皮に包んだものでした。もともとは列車の窓越しに売る「立ち売り」が一般的でしたが、昭和30年代ごろから列車の高速化に伴い、窓が開かなくなり、駅弁の販売が難しくなっていきました。
地方の駅弁の現状
地方では過疎化やモータリゼーションの進行で鉄道利用者が減少。駅の売店が閉鎖され、車内販売が縮小し、廃線も増え、駅弁の売り場も減っていきました。(2023年11月以降には東海道新幹線の車内販売も人手不足で廃止となる予定です。)

このような風景はどの駅でも見られましたが・・・
コロナ禍以前から、地元の駅では売れ行きが落ちていました。例えば、『森のいかめし』の森駅の1日平均乗車数は277人(2019年)、『峠の釜めし』の横川駅は165人(2020年)、『氏家かきめし』の厚岸駅は127人(2019年)、『かにめし』の長万部駅は乗降客数が296人(2018年)です。これらは京王百貨店の駅弁大会で常に上位にランクインする人気駅弁ですが、このような利用客数では経営は難しいでしょう。
救世主の駅弁大会
地方の駅弁は、京王百貨店をはじめとする百貨店の駅弁大会に出店し、マスメディアの報道を通じて知名度を上げ、ふるさとの代表としてのブランドを確立することに成功しました。そして、旅行のマストアイテム(欠かせないもの。 絶対に必要なもの)となり、駅以外の高速道路のサービスエリアや郷土物産の催事でも人気を博すようになりました。
最初に注目されたきっかけは、現在58回を数える毎年1月の京王百貨店主催の駅弁大会(別名『駅弁甲子園』)です。高度経済成長期には旅行熱が高まり、駅弁を味わう人も増えました。その旅先での味を駅弁大会で再体験したいというニーズが広がり、「駅の駅弁」は「ご当地の特別なお弁当」としての認知と人気を高めました。
駅弁大会の開催時期の重要性
百貨店の2月と8月の売上対策としての「ニッパチ対策」がありますが、催事担当統括マネージャーの堀江氏は「夏はありえない」と言っているのを聞きました。
なぜなら、夏の暑さは駧弁の大敵だからです。駅弁は各地から運ばれてきますが、遠隔地からの輸送では時間がかかり、食材が傷むリスクが高まります。真冬の1月は、気温が低く、生ものを扱う実演販売での安全性を考慮すると、駅弁大会には最適な時期です。「1年の始まりに華やかな催しと、おいしい駅弁はふさわしい」という思いも込められています。
コロナ禍と駅弁業界の変化
そうするうちに特急の車内販売がなくなり、コロナの影響で新幹線のサービスも停止しました。感染予防のための外出自粛要請により、駅弁業者の多くが月商の9割以上を失う状況に追い込まれました。

デパートでの大駅弁大会(AIで画像を作ってみました。)
ようやくコロナの規制が緩和されたとはいえ、コロナ禍前のような旅行や出張はまだ難しい状況です。駅弁は旅情を味わえる貴重な食べ物として、京王百貨店の駅弁大会では一度に多くの地域の味を楽しむことができます。
新たな販売戦略
次に、全国的な知名度を得た駅弁業者がターゲットにしたのはスーパーマーケットでした。スーパーの弁当は平均して1個400円程度ですが、駅弁はそれの2倍以上する高価格です。にもかかわらず、駅弁の売れ行きは好調で、スーパーでは駅弁を売る催事が増えています。
コロナ禍をきっかけに、駅弁は百貨店だけでなく、生活に身近なスーパーやネット通販でも販売されるようになりました。決してその方向性は間違ってはいなかったと思います。しかし安全性を後回しにした商売などありえません。
今回の駅弁による食品事故は、スーパーの駅弁大会だけで起きたことでした。
この食品事故は、商社がかかわった配送やスーパーの取り扱いの問題の可能性があるのかもしれません。昭和時代の単純な駅弁の食中毒とは異なり、全国各地のスーパーチェーン店で週末に開催される催事で起きたことが、これまでにない特徴だと指摘されています。
駅では、ターミナル百貨店に出店する有名店の弁当やコンビニ弁当に押され、駅弁は不振に陥っています。しかし、駅以外ではその逆の現象が起こっています。不思議なものですね。
株式会社 松本
https://matumoto.co.jp/
株式会社松本は、食文化と歴史を少しでも多くの方に知ってもらい本物の味を味わってもらいたいと願っております。
この記事を書いているのは、金沢市・近江町市場の一角に店を構える、1958年創業の業務用食品卸会社「株式会社松本」の松本信之です。
当社では、全国でも希少となった選りすぐりの食材を仕入れ、あるいは独自に加工し、全国のホテルや料亭などの飲食業界・フードサービス業の皆様へお届けしています。
■ 私たちの仕事は、食材に“新しい価値”を吹き込むことです
料亭で供される一皿の料理。その一皿の背後には、実に多くの人の手と想いが込められています。
株式会社松本は、そうした日本の繊細な味、美しい料理を支える「食の裏方」でありながら、単なる卸売業ではありません。
私たちは、料理長とともに悩み、考え、試作を重ねながら、食材そのものの提案や新商品開発を行っています。ときには生産現場に足を運び、農家・漁師・海女さんなどの一次生産者や、食品加工業者と連携し、一貫した食材ストーリーを形にします。
「卸売業でありながら、商品企画・開発まで行う」。
気がつけば、私たちは“ファブレス企業”となっていました。
※ファブレス=“ファブ”(工場)+“レス”(ない)。つまり、自社で工場を持たない製造開発型企業のこと。
■「金沢を世界一の美食のまちに」
私たちが目指すのは、ただの商いではありません。
食の魅力を通して、金沢というまちそのものに新しい価値を創造することです。
スペインの小都市・サン・セバスチャンは、人口18万人ながら、わずか10年で星付きレストランが立ち並ぶ“世界一の美食のまち”へと進化を遂げました。いまや世界中からグルメを求めて人々が訪れています。
この「地方都市の成功モデル」を、私たちは金沢にも実現したいのです。
一緒に、新しい味、新しい価値を生み出し、金沢を世界の美食都市へと育てていきませんか?
■ お取引先の一例
嵐山吉兆様、強羅花壇様をはじめとする全国の一流料亭・レストランに加え、
地元・金沢でも、ミシュランガイドで星を獲得されているお店の多くに、長年ご愛顧いただいております。
たとえば、つば甚様、銭屋様、浅田屋様、料理小松様、エンソ様など――
“金沢の味”を支える料理人の皆様と、共に歩んでまいりました。
代表取締役 松本信之
農林水産省認定 6次産業化プランナー
フードアナリスト NO.25042013
【連絡を検討中の企業様へ】
★TEL:076-232-2355
こちらからお電話ください。
(株)松本の代表番号になります。
電話の際は「HPを見た」と言っていただけるとスムーズに対応可能です。
【電話対応時間】平日9:00~16:30
下記の問い合わせフォームでの受付も可能です。
問い合わせフォームは24時間対応しています。
些細なことでも構いませんので上記のリンクからお気軽にどうぞ!
メールアドレスからでもどうぞ!
oishi@matumoto.co.jp